-
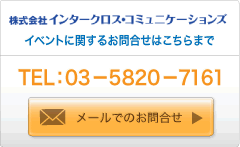
- レポート月別一覧
- 2025年
- 2024年
- 2023年
- 12月
- 11月
- 10月
- 9月
- 8月
- 7月
- 6月
- 5月
- 4月
- 3月
- 2月
- 1月
- 2022年
- 12月
- 11月
- 10月
- 9月
- 8月
- 7月
- 6月
- 5月
- 4月
- 3月
- 2月
- 1月
- 2021年
- 2020年
- 2019年
- 2018年
- 2017年
- 2016年
- 2015年
- 2014年
- 2013年
- 2012年
- 2011年
- 2010年
- 2009年
- 2008年
- 2007年
- イベントレポート
- アニバーサリーイベント
- アミューズメント型イベント
- アート・芸術イベント
- エデュテイメントイベント
- オープニングイベント・セレモニー
- オープン施設ウオッチング
- カルチャーイベント
- コンテスト・コンクール・オーディション
- スポーツイベント
- チャリティイベント
- ファイナルイベント
- ファッションショー
- フェスティバル・祭
- 会議・セミナー
- 動物・ペットイベント
- 参加・体験イベント
- 各種PRイベント
- 国際交流イベント
- 国際会議
- 地域振興イベント
- 季節イベント
- 展覧会
- 店舗回遊型イベント
- 業界レポート
- 物販イベント
- 環境イベント
- 科学イベント
- 空間演出イベント
- 表彰式
- 見本市
- 飲食イベント
- [その他]
- [月刊誌バックナンバー]
- 人気レポートランキング
工事を学び、楽しむ企画展「『工事中!』~立ち入り禁止!? 重機の現場~」@日本科学未来館
2019年2月9日金曜日より、お台場・日本科学未来館の企画展として「『工事中!』~立ち入り禁止!? 重機の現場~」がスタートした。土木・建設の現場は危険が伴うもので、文字通り日常は「立ち入り禁止」。しかし工事現場で活躍する各種重機のファンは多い。今回未来館に展示された、「初の国産油圧ショベル」「ブルドーザ」「ホイールローダ」などは間近で見ると本当に大きく重厚かつ精巧な造りで、迫力満点。これら重機の展示をメインに、「1 土木」「2 建設」「3 再開発」「4 未来」という4つのエリアで映像やパネル、実験展示や体験コーナーなどで工事を紹介している。内容は見て面白く、そして土木建設の技術はもちろん環境・社会などについて子どもでも理解できる構成となっているが、大人でも見たことがないもの、知らないことばかりで大いに楽しめる。
公式サポーターとしてANZEN漫才が起用され、みやぞんが”ほぼ”公式テーマソングを発表。コラボ企画としてオリジナルのお菓子、レトルトカレー、Tシャツなど豊富なグッズをショップで販売。日本科学未来館のカフェでは期間中、工事モチーフのメニューを提供する。 (続きを読む…)
インフラ維持管理に関する初の展示会「社会インフラテック」
現在、高度成長期に造られた道路や橋、水道などの社会インフラの老朽化が進んでいる状況がある。そこで、社会資本の老朽化対策をテーマに、インフラ維持管理者と企業や技術者とのビジネスマッチングを目的とした展示会が東京ビッグサイトで初開催された。ドローン展やハイウェイテクノフェアなど、すでに、インフラ維持管理も目的となる展示会は開催されてきているが、“社会インフラ”を大きなテーマに掲げ、インフラを維持管理する自治体や企業と、効率的なメンテナンス技術や工法を提案する企業のマッチングを目的に開催されたイベントは初となる。IoT、AI、ドローンを活用した技術やノウハウを、ゼネコン、建設コンサルタント、保守・点検・補修、ICT、電機など、インフラメンテナンスに関連する100を超える企業や機関が出展。カンファレンスでは地方公共団体や専門家が多数、登壇し、自治体の老朽化対策、新しいビジネスモデル、インテリジェント・インフラ、コンセッション事例など、多彩なプログラムのカンファレンスも実施。公共インフラの老朽化対策の最新技術・ノウハウから、IoT、AI、ドローンを活用したインテリジェント・インフラまで、幅広くインフラメンテナンスの最前線を紹介した。新しい時代に向けて、今後は、インフラをどのように守り、使っていくのか、社会全体で取り組むことが求められている。本展は、開催20回を迎える環境総合展「エコプロ2018」や、「第3回ナノセルロース展」、移動の未来をテーマにしたイベント「TRAN/SUM」と同時開催し、合計で約16万人が来場した。次回は、2019年12月上旬に東京ビッグサイト南展示ホールで開催予定だ。
東京ビッグサイト 東ホール
伝統を継承し、新たな文化を創出する文化・精神・価値の文化交流・発信拠点として、「神田明神文化交流館『EDOCCO』オープン」
約1300年の歴史をもち、神田・日本橋・秋葉原・大手町・丸の内地区の氏神さまである神田明神は、「伝統と革新」をコンセプトに、伝統を継承し、新たな文化を創出する文化・精神・価値の文化交流・発信拠点として、神田明神文化交流館「EDOCCO(えどっこ)」を開業した。建物は地下1階地上4階建て。神札授与所のほか、物販・飲食スペース(「EDOCCO SHOP -IKI IKI-」・「EDOCCO CAFE -MASU MASU-」)、多目的ホール(「神田明神ホール」)、貴賓室(「EDOCCO LOUNGE」)、日本文化体験スペース(「EDOCCO STUDIO」)の5フロアで構成されている。
ホワイエだけでなく、デッキと一体となって使用することができる最大着席約400名、スタンディング約700名収容の「神田明神ホール」は、商売繁昌や良縁成就の神様に見守られながら、セミナー、講演、各種式典、製品発表会などに利用が可能。“ジャパンカルチャー”の発信地として、ライブ・コンサートを中心としたエンターテインメント空間としても利用ができるイベントホールとなる。日本の古典芸能、着物や食などの伝統文化の体験ができる「EDOCCO STUDIO」は、日本文化体験施設であり、外国人観光客に向けて国際交流も図る場となる。神道体験・日本文化体験を組み合わせることで、MICEやユニークベニューの場としての文化交流も期待されている。 (c)ナカサ&パートナーズ 河野政人
神田明神文化交流館「EDOCCO」オープン
ものづくりイベントを随時開催し、地域コミュニティーを育む商業施設「マチノマ大森」オープン
大田区大森西エリアに「マチノマ大森」がグランドオープンした。場所は都心にも近い大田区の住宅地で人口は多いが、最も近い最寄り駅が徒歩10分の大森町で、近くを通るJR京浜東北線の蒲田駅と大森駅からはちょうど中間地点に位置するため両駅を利用しにくい。そんな立地に三菱商事都市開発が手掛けたこの商業施設は、従来のショッピングセンターにはない特徴をいくつか備えている。
1)計画段階より大田区と連携し、ハード面では保育所や地域防災倉庫の設置、ソフトコンテンツでは大田区のものづくりや物産の情報発信拠点として機能する
2)コミュニティースペース「マチノマノマ」を創設。子育て世代からシニアまで、地域住民が交流できるスペースの提供と各種イベントの企画運営を行う
3)スーパーマーケット「ライフ」をメインに、医療・ペットショップなど生活に欠かせないサービスを提供するテナントが集結している
インタビューはオープンから2週間後だったが、早くも顧客からの反響に手ごたえを感じているという担当者に、この施設が実現するまでの経緯と企画意図をきいた。
「渋谷de阿波おどり」や「徳島料理フェア」 ~徳島県が東急グループの協力のもと「渋谷で徳島SHOW」を開催
再開発でますます賑わう渋谷の街を舞台にこの秋、徳島県が積極的なプロモーションイベントを展開した。東急グループ各社の協力のもとで実施された催しは「徳島物産展」(東急百貨店東横店)、「徳島料理フェア」(渋谷エクセルホテル東急、渋谷東急REIホテル)、「渋谷de阿波おどり」(渋谷マークシティ)など。10日(土)に開催された「渋谷de阿波おどり」にはアイドルグループ「STU48」のメンバーも参加、後藤田徳島県副知事も来場して賑わう休日の渋谷で盛大に阿波おどりを披露し、徳島の魅力を大いにアピールした。
地方自治体とグループ企業が横断的にプロモーションを展開するという例は珍しいが、なぜ実現できたのか。インタビューでは徳島県・東急グループの担当者に協働がどのように進められてきたかについて経緯を聞いた。 (続きを読む…)
アウトオブキッザニアイベント「洪水から身を守る仕事体験 in 荒川」
キッザニアを飛び出し、普段、入ることのできない場所での仕事体験ができるアウトオブ゙キッザニアで、国土交通省の新人職員として、災害対策室で大型台風が接近した時の仕事体験ができるプログラムが開催された。水防災の普及啓発を目的に、国土交通省関東地方整備局荒川下流河川事務所と、子どもの職業・社会体験施設のキッザニアがタッグを組んだ。国土交通省が、洪水などの被害を最小限にするために行っているさまざまな取り組みを知るとともに、自分自身の身を守るための洪水リスクを考える内容だ。さまざまな仕事にチャレンジして社会の仕組みを学ぶことができるキッザニアのプログラムのなかでも、国土交通省の河川事務所との連携企画となる仕事体験は初めて。総計90人(各回:30人)の定員は約1週間で埋まる人気ぶりで、大規模な自然災害も頻発しているなか、親子の注目を集めたようだ。プログラムの内容は、「荒川の歴史について知る学び」、「洪水対応訓練(仕事体験)」、あらかじめ災害に対して「どんな準備が必要か」「どのタイミングで逃げるか」を決めておくマイタイムラインを作成する「マイタイムライン作成研修」の3本立て。子どもたちは、見学席で家族が見守るなか、先輩職員のレクチャーを受けて、各グループ内で決められた役割を、それぞれのタイムラインに沿って進行する洪水対応訓練を体験。終了後、「楽しかった」「よく分かった」と話していた。
(続きを読む…)
荒川下流河川事務所 災害対策室・荒川知水資料館(アモア)
小田急百貨店が“観覧無料の映画館”に! 昨年初開催で好評のイベントの第2回「小田急ショートショートシアター」
小田急百貨店新宿店のフロアを“観覧無料の映画館”に仕立て、米国アカデミー賞公認・アジア最大級の国際短編映画祭ショートショート フィルムフェスティバル & アジア(SSFF & ASIA)の出品作品を中心に上映する特別企画「小田急ショートショートシアター」が開催された。初開催の昨年は、約1万人が来場。第2回目の今年は昨年以上の盛況となった。ショートフィルム作品に加え、落語や読み聞かせなどライブ感あるイベントも新たに追加され、より幅広い世代が楽しめる非日常へのショート・トリップ空間となっていた。日頃は催事が開催されている同店11階会場に足を踏み入れると、明かりを落としたフロアは映画館さながら。取材したのは平日だったが、入れ替え制のシアターには幅広い年代の人たちが行列をなし、また、通りすがりに立ち寄ってしばらく立ち見で鑑賞していく人もかなり多いようだった。百貨店の顧客と映画ファン双方の顧客を呼び込み、互いに拡大する試みとしての成功例といえそうだ。 (続きを読む…)
東京都の事業「Old meets New 東京150年」のメインイベント「東京150年祭」
平成30年(2018年)が江戸から東京への改称、東京府開設から150年の節目であることを記念し、東京都が今年、展開している事業「Old meets New 東京150年」のメインイベントとなる「東京150年祭」が、浜離宮恩賜庭園で開催された。目玉企画は、夜の庭園で実施されたプロジェクションマッピング「刻をあそぶ時空の旅 初音ミクLinks Tokyo150」。潮入の池に、幅30メートル高さ15メートルのウォータースクリーンを設置し、背後の木々にも、プロジェクションマッピングを投影。バーチャルシンガーとして世界中で人気の初音ミクが、明治、大正、昭和、平成のファッションを計14着衣装替えして、39曲の楽曲をメドレー形式で歌い、東京の過去、現在、未来を表現する演出で、国内外に東京の魅力を発信した。上映時間は各回約18分で、各日4回上映。いずれの回も、入場整理券は配布終了となり、初音ミクのグッズはイベント初日に全て完売。回を重ねて観賞するファンの姿も見られるほどの人気となった。ほかにも、全身スキャンで撮影した来場者の3Dアバターが、初音ミクと「東京2020音頭」を踊る「デジタル盆踊り」や、150年前にタイムスリップして記念撮影できるデジタル記念撮影など、最新技術を活用したコンテンツを用意。秋の空の下での野点体験や東京都パラリンピック体験プログラムなども展開し、東京の魅力「伝統と革新」をPRするとともに、記念の節目を都民とともに祝うイベントとなった。
浜離宮恩賜庭園
東急グループが2027年まで進める渋谷再開発事業の全貌
東急電鉄は、世界を牽引する新しいビジネスやカルチャーを発信するステージとして、「エンタテイメントシティSHIBUYA」の実現を目指し、2012年の渋谷ヒカリエの開業を皮切りに、駅周辺において大規模な開発プロジェクトを関係者と協力して推進してきた。2017年には、渋谷と原宿を結ぶキャットストリートの起点に位置する「渋谷キャスト」、2018年9月に「渋谷ストリーム」と「渋谷ブリッジ」が開業。2027年まで続く渋谷再開発プロジェクトは、残り4つとなる。取り組むのは、魅力的な街イベントのグローバル発信や、ベンチャーエコシステム、クリエイティブ産業の集積などを通した、“SHIBUYA”のブランド化の推進だ。渋谷駅周辺での年末カウントダウンや盆踊りなど、街ぐるみでの取り組みも世界に発信し、「世界のSHIBUYA」を目指したいとしている。後編では、現在進行中のプロジェクトの概要、産業集積の柱となりうるエース企業の誘致等によって大きく進む、渋谷ビットバレー再興の様子もレポートする。
「渋谷ストリーム」「渋谷ブリッジ」オープン
旧東横線渋谷駅のホーム、線路跡地およびその周辺地区を再開発した大規模複合施設「渋谷ストリーム」と「渋谷ブリッジ」の一部がオープンした。「渋谷ストリーム」は、クリエイティブな大人のためのグルメやオフィス、ホテルなどが集まり、渋谷駅の南側とその周辺エリアとなる “渋南” の拠点となる。渋谷と代官山の中間点に、かけ橋となる複合施設「渋谷ブリッジ」は、ホテルや保育所型認定子ども園を通して、多世代・異文化の交流を生み、地域を盛り上げる。両施設のオープンに伴い、官民連携によって渋谷川や遊歩道も整備。渋谷~代官山エリアの回遊性を高めるとともに、賑わいと憩いが創出され、クリエイティブワーカーを魅了するエリアへと変貌する。前編となる本レポートでは、「渋谷ストリーム」と「渋谷ブリッジ」、および、渋谷川の遊歩道におけるイベントスペースの活用について紹介する。続く後編では、2027年に完成予定となる渋谷駅周辺再開発プロジェクト全体についてレポートする。
渋谷ストリーム、渋谷ブリッジ
東京都が「ラグビーワールドカップ2019™日本大会1年前イベント」を銀座で開催
東京都は、2019年9月~11月に日本全国12会場で行われるラグビーワールドカップ2019™日本大会の開幕1年前を記念し、銀座で1年前イベントを開催した。開催都市特別サポーターとしてお笑い芸人の渡部建さん、女優の山崎紘菜さん、現役ラグビー選手畠山健介さんが就任し、3名はその後行われたトークショーにも登場した。銀座の交差点に面した会場ということで通りすがりに立ち寄ってラグビー体験やアンケートに参加する人も多かった。子どもたちがラグビーボールでキャッチボールをしたり、キックに挑戦することができる体験コーナーでは社会人ラガーマンたちが基礎を教えて一緒に遊びながらサポート。後半には急遽小池都知事も会場を訪れ、ラグビー体験のパフォーマンスを披露するとともに、ラグビーの楽しさをPRした。今までラグビーをあまり見たことがない一般の人たちにも2019年のラグビーワールドカップへ気軽に足を運んで欲しいという主催者の意気込みが大いに伝わってくるイベントだった。 (続きを読む…)
2018年国際水協会(IWA)世界会議・展示会にて一般向けサイドイベント『それってホント?世界の水問題と日本の水事情!!』を開催
2018年国際水協会(IWA)世界会議・展示会は9月16日(日)に開幕し、開会式には皇太子ご夫妻が出席され、開催国委員会会長を務める小池百合子知事のあいさつもあった。同会議は2年に1回開催される国際会議で、初の日本開催となる。21日まで6日間の会期中には98か国約9,800人が参加した。上下水道などの水分野の産学官の専門家が一堂に会する貴重な機会であるが、一般の人にとってはなじみがなく、国際会議が開催されることすら認識されにくい。しかし今回、一般の人が参加できるサイドイベントを開催して水問題への理解を深めようという試みが実施された。本会議場である東京ビッグサイトに近い会場で、17日のイベントは3部構成で行われ、幅広い年代の多様な参加者が楽しみながら水の知識を学んでいた。
「高校生による研究発表」…期待以上にハイレベルな研究発表に、聴講の大人も真剣に質問をぶつける場面があった。
「水に関するトーク&体験」…タレント峯岸みなみさんをゲストに水の問題を身近に考えるトークや水技術の実演・体験展示があった。
「シンポジウム」…水関連企業の発表の後、一般の人にもわかりやすい切り口でのディスカッションが開催された。 (続きを読む…)
TFTホール
地方創生に向けた多業種連携シンポジウム『共創の日2018』
内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局が主催し、実施主体となる全国農業協同組合中央会、全国森林組合連合会、全国漁業協同組合連合会、全国商工会連合会、日本商工会議所の5団体が連携した、地方創生に向けた多業種連携シンポジウム&フェアイベント『共創の日2018』が開催された。
本シンポジウムは、地方創生を実現するにあたり、地域のさまざまな産業の発展と所得向上を通じた地域経済の活性化が必要であり、そのためには、多くの地域において、業種の枠を超えた民間団体の積極的な相互連携が不可欠であることから、全国各地の団体や企業等が参加のもと、農林漁業や商工業の業種の枠を超えて、相互に連携した取り組みのモデル事例を広く普及し、多業種連携を加速化することを目的に行われたもの。
“共創フェア”として、一般を対象にした、農林漁業と商工業の“共創”により生まれた特産品の展示・販売イベントも実施。会場となった国際フォーラムの地上広場も含めて20のブースが出展し、東京ではあまり手に入らない商品の展示販売を行った。今後も、シンポジウムとフェアとの同時開催を継続開催していく意向だ。
(続きを読む…)
東京国際フォーラム (シンポジウム:5階 ホールB5 フェア:1階地上広場、地下2階ホールE2)
多摩・島しょ地域における「新たなツーリズム開発支援事業」スタート&キックオフイベント
東京都と公益財団法人東京観光財団は、多摩・島しょ地域で、新たに体験型・交流型の観光スポット開発等を行う事業に対し、必要な経費の一部助成等の支援を行う「新たなツーリズム開発支援事業」を開始する。プロジェクトの申請受け付けは、9月10日(月)から10月19日(金)まで。申請後、審査を経たうえで、特に優れた事業をモデルプロジェクトおよび助成対象事業として4件程度、採択。助成対象期間は最長3年間とし、1年目は、助成対象と認められる経費の3分の2以内(助成限度額500万円)、2年目は助成対象と認められる経費の2分の1以内(助成限度額375万円)、3年目は助成対象と認められる経費の3分の1以内(助成限度額250万円)が受けられるほか、事業プロモーターから、広報に向けての実施のアドバイスもある。
9月12日には、支援事業の開始に伴ったキックオフイベントを実施。ケーススタディとして、多摩地域・島しょ地域で、グランピング(=「グラマラス×キャンピング」:豪華なテントにベッドなどの家具を備え付け、食事も提供されるキャンプ)の施設やゲストハウスの開設の取り組みを行う事業者や、全国でゲストハウス文化を広めているコンセプトメーカーが登壇。観光ビジネスとしての多摩・島しょ地域の可能性についてのトークセッションも行った。東京都の観光の一事業のなかで、全国からのゲストも招いたキックオフイベントが実施されるのは、珍しい。
オリンピック開催を一つの契機とし、多摩・島しょ地域にも観光客を呼び込める事業を定着させていく意向だ。
(続きを読む…)
3×3 Lab Future
GUNDAM BASE TOKYO 1周年の夏休み、親子で遊べる「ガンダムビルドダイバーズフェスティバル2018」開催
株式会社BANDAI SPIRITSと三井不動産商業マネジメント株式会社は、「機動戦士ガンダム」シリーズのテレビアニメーション最新作『ガンダムビルドダイバーズ』(テレビ東京系列)を中心に、ガンダムとガンプラの魅力を発信するイベント『ガンダムビルドファイターズフェスティバル2018』を開催した。「THE GUNDAM BASE TOKYO」(ダイバーシティ東京プラザ館7階)ではオープン1周年記念として各種の企画を実施した。
そのなかで特に注目されたのは今回初公開された「ガンプラバトルラボラトリー」だ。カスタマイズした自分のガンプラをスキャンして、3Dデータ作成→デジタルのゲームの世界でガンプラバトルを行うというもの。アニメの中の「ガンプラバトル」が遂に現実になりつつあるということで話題を呼んでいる。他には組み立て教室や初公開の新アイテムを含むガンプラ展示などがあり、ガンプラを「見て、作って、遊んで」楽しめる体験施設で親子が世代を超えて楽しむ姿があった。
イベント期間中は夏休みということでひときわ賑わうお台場・ダイバーシティ。その各階エレベーターや柱にはガンプラやキャラクターの装飾が施され、フェスティバル広場の「実物大ユニコーンガンダム立像」と合わせ、館の随所でガンダムの世界観を表現するとともに、1周年のお祝いムードを盛り上げていた。 (続きを読む…)
落合陽一×日本フィル プロジェクトVOL.2「変態する音楽会」テクノロジーの力で生まれ変わるオーケストラと音楽
テクノロジーの力を使って、聴覚障害のある人を対象にしたクラシックコンサート「落合陽一×日本フィル プロジェクトVOL.1《耳で聴かない音楽会》」から4ヶ月。ネクストステージとなるVOL.2では、1,500席の大ホールとなる東京オペラシティ コンサートホールの舞台に、80名近いフルオーケストラが登場。聴覚障害のある人だけでなく、誰でも触覚や視覚を通して身体で音楽を楽しめるクラシックコンサートへと、テーマも規模もスケールアップして開催された。VOL.1同様、クラウドファンディングも実施し、新たな試みに対する期待値の高さから、目標金額の200万円を大きく上回る500万円を集めている。
今回の音楽会の大きな特徴は、ビジュアルデザインスタジオ「WOW」と協働した映像表現だ。
指揮者が振るタクトに合わせて、WOWがステージに吊り下げられた縦長の巨大LEDスクリーンの色を変化させたり、模様が変わったりするビジュアル演出・演奏を生で行った。映像も一つの楽器として含まれ、その場でライブで生成されて、演奏(表現)された形だ。映像も音も対等な関係で、オーケストラとして再構築されることで、オーケストラの旧来のスタイルそのものを“トランスフォーム(変態)”しようとした。会場には新しい音楽体験をすることに対しての期待をもった来場者が多く、「現代の魔法使い」とも呼ばれ、メディアアーティストとして注目を集める落合陽一さんのファンらしき若い人も多く、従来のクラシックファンとは、また異なる層が訪れていたようだ。(写真:©山口敦)
東京オペラシティ コンサートホール
廃校が増える中、自治体関係者や企業等によるディスカッション「廃校サミット2018」
今、人口減少を受けて、日本各地で廃校が増えている。その数は年間、約500校。平成14年から27年度までの14年間に廃校となった数は、6,811校にものぼる。現存する廃校施設のうち、約7割は様々な用途に活用されており、学校や社会体育施設、社会教育施設・文化施設などのほか、企業の工場やオフィスなどの施設、創業支援施設としても活用されている。カフェになったり、宿泊施設になったり、アートセンターとして文化拠点になったり、フェス会場にもなったりと、廃校は、今、人が集まる新しいコミュニティの場として再生され、廃校という話題性から、メディアの注目も集めている。
しかし、まだ、活用用途が決まっていない廃校も約2割、1,200校以上ある(平成27年度)。廃校は、ただ活用すればいいというものではなく、地域の実情やニーズにより有効活用することが求められる。そんななか、廃校を保有する自治体関係者や廃校活用を考えている企業等を対象に、廃校活用をテーマとした3つのイベントが、8月8日から9日にかけて同時開催された。廃校活用の事例を紹介し、実際に廃校施設と活用ニーズを「つなぐ」ことを目的としたマッチングイベント「廃校活用マッチングイベント」、廃校利用と地域経済の活性化、地方創生をテーマに講演やパネルディスカッション等を実施した「日経地方創生フォーラム」、都内7施設の協力のもと、廃校利活用施設を見学した「特別見学会」だ。「廃校活用マッチングイベント」を中心に、それぞれのイベントの様子もレポートする。
【廃校活用マッチングイベント】文部科学省講堂 【日経地方創生フォーラム】六本木アカデミーヒルズホールタワーホール 【特別見学会】都内7施設
2年後に向けて花を咲かせよう!東京2020パラリンピックカウントダウンイベント~みんなのTokyo 2020 2 Years to Go!~を開催!
東京2020パラリンピック競技大会の開催まで2年前の節目となる8月25日(土)、お台場パレットタウンの中にある「MEGA WEB(メガウェブ)」をはじめとした臨海副都心エリアでカウントダウンイベントが開催された。MEGA WEBで実施されたセレモニーには、パラアスリートとして、バドミントンの里見紗李奈(さりな)選手、カヌーの小山 真(まこと)選手、自転車競技の川本翔大選手、ゴールボールの天摩由貴選手、ボートの前田大介選手、射撃の田口亜紀さんの6名が参加。ゲストに東京2020パラリンピック競技大会に向けての国際パラリンピック委員会 特別親善大使を務める香取慎吾さんがゲストとして登場し、前田大介さん(ボート/アテネ2004大会 水泳200mメドレーリレー 銀メダル)と、ボート競技の水上での動きを再現するエルゴメーターを使用したボート対決を行い、ボート競技の魅力を発信した。MEGA WEB には、パートナー企業や会場関連自治体が20ブース出展。パラリンピック競技体験や先端技術を活用した体験等のブース出展を行い、ファミリー層を中心に賑わっていた。当日は、MEGA WEBのほか、シンボルプロムナード公園(夢の公園)や日本財団パラアリーナでもパラスポーツ体験ができるイベントを開催。臨海副都心エリアにあるパナソニックセンター東京「SUMMER FEST 2018」、「国立研究開発法人技術総合研究所臨海副都心センター」でも、アスリートによるトークショーや義足体験などの連携イベントを展開し、東京2020パラリンピック大会で多くの競技種目の会場となる臨海副都心エリア一帯となって、開催2年目を盛り上げた。
MEGA WEB(メガウェブ)、シンボルプロムナード公園(夢の広場)、 日本財団パラアリーナ
台東区発、まちの多彩な芸能・芸術・文化を愉しみ、継承する「江戸まち たいとう芸楽祭」
台東区では今までに「したまちコメディ映画祭(したコメ)」「したまち演劇祭」などを実施し、地域の文化・芸術振興に資するイベントの実績を重ねてきた。これらの取り組みについては一定の成果を上げたということで2017年度までに終了し、2018年、より幅広く地域の芸能・芸術・文化を楽しみかつ新興・継承していく新たな枠組みとして「江戸まち たいとう芸楽祭」をスタートさせることとなった。
過去の催しが「映画」「演劇」をテーマとしたものだったのに対して、新しい芸楽祭は2018年の夏から翌年の2月までを「夏の陣」「冬の陣」の2期に分け、映画・演劇・伝統行事・まち歩きイベント・伝統芸能のワークショップなど、地域に根付く多彩な文化・芸術を広くとりあげ、参加型の催しなどを実施していく。過去に取材した“したコメ”は多くのボランティアが支えていたが、今回はさらにボランティアの役割が大きくなり、計画段階から協力を得て準備を進めてきたそうだ。今後1年間の盛り上がりに注目したい。 (続きを読む…)
子どもや若者にモノづくりの魅力を発信「モノづくり体感スタジアム2018」
「モノづくり日本会議」では、子どもや若者にモノづくりの魅力を発信する事業として、モノづくりに関するワークショップや理科・科学教室を一堂に会する親子向けのイベント「モノづくり体感スタジアム」を2009年より実施している。開催9年目を迎えた今年は、小学校1年生から6年生をコアターゲットに、1,456名の来場者が参加(同伴保護者を除く)。モノづくりに関連する11社・団体が出展しており、5年前からは、全日本製造業コマ大戦協会による「子どもコマ大戦 モノづくり体感スタジアム場所」も展開している。回を重ねるにつれ、イベントの内容も、以前の「モノづくり」一辺倒から、「ロボット」「プログラミング」「環境・エネルギー」へと変化しているようだ。近年の傾向としては、大学や高等専門学校も子供向けの体験型プログラムを提供している。今年のイベントの参加各社・団体の内容をまとめた。
TEPIA




















